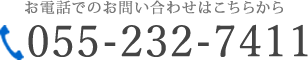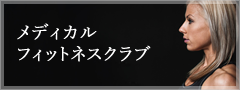講演「老化は足から、予防して元気で長生きの秘訣」
今井整形外科医院 » 講演「老化は足から、予防して元気で長生きの秘訣」
今井整形外科医院 今井大助

年を取ると、下半身から衰えてきます。足腰が弱ってくると、一人で立ち上がれない、歩けない、そうなると人の手を借りなければならなくなってきます。自分で歩けなくなると、車椅子、そして寝たきりにつながり、体の機能全体が徐々に弱っていきます。寝たきりや介護が必要な高齢者の原因の多くを占めるのが、運動器症候群、すなわちロコモティブシンドロームです。これは『骨、関節、筋肉などの運動器の働きが衰え、暮らしの中の自立度が低下し、要介護の可能性が高い状態、あるいは既に要介護になっている状態』と定義され、2007年に提唱されました。
ロコモの原因としては、大きく二つに分けられます。一つは運動器自体の疾患である変形性関節症、脊柱管狭窄症、骨粗鬆症などであり、ロコモの3大疾患と言われるものです。もう一つは、年を取ること自体によって自然におこる、筋力やバランス感覚の低下等による運動器機能不全、廃用性萎縮、サルコペニヤが原因と言えます。
日本人の平均寿命は男性が約80歳、女性は約86歳ですが、健康寿命の平均は男性が約70歳、女性は約74歳と言われています。平均寿命と健康寿命には約10年間の開きがあり、この間は自立した生活ができない状態にあると言われています。現在の要支援、要介護の原因として4、5位が関節疾患、転倒・骨折と、どちらもロコモが関係しています。高齢者の骨折は骨粗鬆症と大きく関係しているので、骨粗鬆症とそれによる骨折をいかに予防するか、とても重要になってきます。
ロコモにならないための運動、ロコモーショントレーニングを紹介します。目的は運動器の機能を維持し、転倒骨折を予防することです。一つ目は開眼片足立ちです。片足で立つことによって、両足で立っている場合に比べて約3倍の負担が足にかかっています。これを左右それぞれ1分間、1日3回行います。二つ目はスクワットです。膝を曲げるときに、膝がつま先より前に出ないよう、椅子に腰を下ろすイメージでゆっくりしゃがみこんでいきます。これを一度に10回ずつ、1日30回を目標にします。
実際に私どもの通所リハビリに通う、介護認定(要支援1~要介護3)を受けている男女合わせて34人(平均年齢74.7歳)の運動実験結果を示します。週2回、平均12ヶ月間のトレーニングを行い、片足起立時間、10m歩行速度、Timed Up & Go Testの3つの項目で評価した結果、すべてにおいて、トレーニング前と比べて成果を上げました。また私どもの老人保健施設で実践した、介護認定を受けていない男女合わせて44人(平均年齢81.6歳)を対象とした運動機能向上事業でも、同様にある一定の成果を上げました。このようにトレーニングを続ければ必ず効果が表れます。
高齢者でもトレーニングにより筋肉量は増え、転倒予防につながります。ロコモにならないようまだ種のあるうちに鍛え予防することが、元気で長生きの秘訣であります。是非今日からみなさんも実践してみましょう。
(平成27年3月14日(土) 甲府市医師会主催・第63回医療懇話会 於:山梨県立文学館)